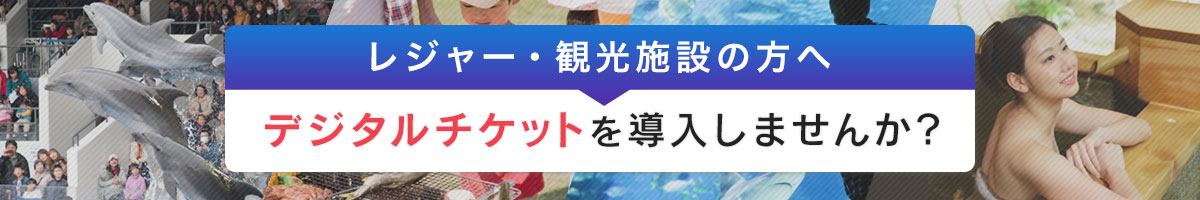「やっぱり知りたい!日本の政治改革」 in京都
イベントは終了しました
やっぱり知りたい!日本の政治改革
第一回 戦後日本の「政治改革」―90年代政治改革を問い直す ・・・2018年4月1日(土) 18:00-20:00
1990年代前半、日本政治は「政治改革」の時代を迎えていました。冷戦体制の崩壊、バブル経済の終焉など、当時の日本を取り巻く状況が劇的に変化する中で、自民党の一党優位体制は限界を露呈し、学者、メディア、一般市民、そして政治家をも巻き込んだ改革論争が行われました。その過程で、選挙制度改革を中心とした政治改革が達成され、政権交代可能な政治システムの構築及び、汚職や腐敗を防止するための諸制度の整備が実現しました。しかし、改革から20年以上が経過した現在、目指されていた政治の姿は未だ私たちの前に現れていません。政治改革は間違っていたのでしょうか?政治学者たちの間でも意見は割れています。今回の講義では、1990年代の政治改革が何を根拠に展開され、何が目指されていたのかを確認することで、今日の政治状況をもたらしている制度の来歴をたずねます。その際、流動化していく政治家や政党の動きも追いつつ、学問、とりわけ政治学が果たしてきた役割にも着目します。政治改革の時代は、日本で例外的と言っても言いほど、政治学が強い影響力をもった時代でした。それらの解説を通じて、今日の政治状況をもたらした一因を明らかにするのが今回の講義の目的です。それを果たしたうえで、これからの政治について考える手がかりを提供し、議論したいと考えています。

1990年兵庫県生まれ。京都府立大学公共政策学部卒業。京都大学大学院人間・環境学研究科修士課程修了。現在、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程在籍中。専攻は公共政策学。現在の関心は、科学的根拠の政策活用についてを理論・ケースを用いて論じること。
第二回 戦前日本の「政治改革」―明治憲法体制の桎梏・・・2018年4月15日(土) 18:00-20:00
戦前日本の「政治改革」の目的は、明治憲法体制の特質であった権力の割拠性をどのように克服して、統合された政治指導力を確立するかにありました。あえて言えば「一強」を生み出そうとする「政治改革」でした。
なぜそのような「政治改革」が必要だったのか。明治憲法が政治権力を様々な国家機関に切り分けていたことに原因があります。なぜ明治憲法はそのような体制を敷いたのか。そこにはまた原因があります。このように本報告ではまず前提として、なぜ「政治改革」が必要とされる状況が生じたのか、その源流を辿っていきます。
次にその「政治改革」がいかなる結末を辿ったのかを明らかにします。結論を言えば、アジア・太平洋戦争の敗戦は「政治改革」の失敗の結果であり、同時に明治憲法体制の破綻を意味しました。
この歴史的経験から私たちが何を学べるかを議論したいと思います。歴史学とは、過去を見ることで現在を展望していく学問です。今日の政治や社会を考える手がかりは、常に歴史の中にあります。安易に比較することも出来ませんが、かといって全く無関係であると切り捨てることも出来ません。戦前の「政治改革」から得られる経験の意味とは何か。皆様と一緒に考えていければと思っています。

1990年兵庫県生まれ。島根大学法文学部社会文化学科卒業。京都府立大学大学院文学研究科史学専攻修了(歴史学修士)。現在、自治体非常勤職員。
論文 島根県における憲政会・立憲民政党勢力の形成と展開(『山陰研究』第10号、2018年)(3月掲載予定)。
自治体非常勤職員を務めつつ、日本の政治史に関する研究を進める。
日時:
第一回 戦後日本の「政治改革」―90年代政治改革を問い直す ・・・2018年4月1日(土) 18:00-20:00
第二回 戦前日本の「政治改革」―明治憲法体制の桎梏・・・2018年4月15日(土) 18:00-20:00
初級編
御厨貴ほか編『政権交代を超えて』(岩波書店、2013年)
民主党政権が瓦解した後、自民党・民主党をはじめとした政治家たちへ行ったインタビューと、三世代の政治学者(御厨貴・牧原出・佐藤信)の鼎談及び論考が収録された本です。政治学者でも世代によって政治の受け止め方が異なることが分かるほか、政治家たちが何を考え、どう行動してきたかもわかる内容となっています。
薬師寺克行『現代日本政治史』(有斐閣、2014年)
朝日新聞の元記者による政治史です。1990年代以降の政治の動きを概括的に手際よく整理することで、現代政治を見渡せる視座を提供してくれています。
中級編
後藤謙次『平成政治史』(岩波書店 全三巻、2014年)
元共同通信記者で現在もテレビ等で活躍するジャーナリストによる圧巻の政治史です。当時、記者だったからこそ知りえる裏話などが政治史の理解に立体感を与えてくれます。
中北浩爾『自民党』(中公新書、2017年)
結局のところ、自民党は強いのか、弱いのか。本書は自民党の歴史を丁寧に振り返ることで今日の自民党の姿をステレオタイプから離れたかたちで提示した一冊です。内容が充実しているだけでなく、記述も平易ですのでお勧めです。
上級編
砂原庸介『分裂と統合の日本政治』(千倉書房、2017年)
政治システムの不安定さや統合力の弱さの原因が地方政治と国政政治の歪な構造にあることを突き止めた研究です。大佛次郎論壇賞を受賞した本書は、政治を論じる上で地方の存在が重要であり、それを見逃してきた改革路線に見直しを迫っています。
建林正彦『政党政治の制度分析』(千倉書房、2017年)
政党システムを多角的な視点(マルチレベル)から分析し、政治改革が内包していた問題点や課題を浮き彫りにし、望ましい制度のあり方を提言した一冊です。計量分析や緻密な文献調査を踏まえた政治学の最新成果であり、今後の政治議論は本書を抜きには語れないでしょう。
初級編
筒井清忠『昭和戦前期の政党政治』(筑摩書房、2012年)
本講義で多くの時間を割く政党政治について書かれた本です。戦前の政党政治から現代でも学べる視座を得られます。
坂野潤治『日本近代史』(筑摩書房、2012年)
政治史研究の第一線を走ってきた著者が描く通史です。大部な本ですが、明治から日中戦争までの歴史を一気に通観出来ます。
北岡伸一『日本政治史 増補版』(有斐閣、2017年)
明治から戦後までの政治史が一気に概観できる一冊です。あくまで中央の政治史に力点が置かれていますが、本講義の視座と重なるところも多く、政治史の入門書としても優れています。
中級編
粟屋憲太郎『昭和の政党』(岩波書店、2007年)(初版は1983年)
政党政治史を考える上で不可欠な一冊です。初版から既に30年を数えますが、未だにこれを超える概説書はありません。不朽の名著です。
古川隆久『ポツダム宣言と軍国日本』(吉川弘文館、2014年)
明治憲法体制の中に敗戦の原因を位置付けています。特に戦前の日本政治で重要な位置を占めた軍部の抱えていた問題が理解できる一冊です。
川口暁弘『ふたつの憲法と日本人』(吉川弘文館、2017年)
日本人にとって、憲法とは何かを解き明かした一冊です。明治憲法と日本国憲法の二つの憲法から、日本における憲法の史的特質を描いています。
源川真希『総力戦のなかの日本政治』(吉川弘文館、2017年)
本報告でも触れることになる大政翼賛会がいかなる目的を以て誕生したのか。そこに至る政治指導層の思惑と「政治改革」の結末が描かれています。戦時期日本を扱った最新の通史です。
上級編
池田順『日本ファシズム体制史論』(校倉書房、1997年)
政党内閣崩壊後の日本政治について、各省間の対立や国家機構の再編過程を描いた一冊です。前半では二・二六事件後から日中戦争にかけての国家機構改革の顛末が、後半では地方をどのように国家権力が掌握するかをめぐって省庁間で起きた対立が克明に描かれています。
米山忠寛『昭和立憲制の再建』(千倉書房、2015年)
政党内閣崩壊から敗戦までの政治過程を立憲制の危機、再編、再建の時代として大胆に描き直した一冊です。特に近年研究の進展が著しい戦時期の議会勢力の動向に着目し、彼らが明治憲法を積極的に引用して自らの存在意義を主張した点などを明らかにしています。
小関素明『日本近代主権と立憲政体構想』(日本評論社、2014年)
明治維新から戦後初期までの政治家と知識人の政体構想を中心に扱っています。著者は二大政党制を支持する立場ですが、単にアメリカやイギリスに倣うべきであるというような単純な理論ではなく、戦前戦後の政治家や知識人の言説や実際の政治過程と今日の政権交代の失敗を踏まえた上で、二大政党制と政権交代の有効性とそれが機能する条件を導出した稀有な研究です。
コメント
チケット情報
このチケットは主催者が発行・販売します
政治改革割(全2回通しチケット)
第一回 戦後日本の「政治改革」―90年代政治改革を問い直す2018年4月1日(日) 18:00-20:00
第二回 戦前日本の「政治改革」―明治憲法体制の桎梏2018年4月15日(日) 18:00-20:00
販売条件
・イベント予約完了後のチケット代はご返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
お支払い方法
チケットの取出し方法
お問い合わせ先
- メールアドレス
このイベントを見ている人にオススメ
読み込み中