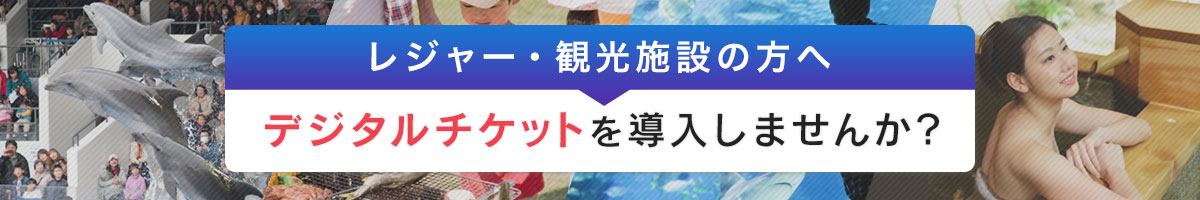第6回ESIBLA教育フォーラム
イベントは終了しました
高等学校では2022年度から新しい学習指導要領が実施されます。新しい学習指導要領では、授業を通して「何ができるようになるのか」という観点から、「学びに向かう力・人間性」、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」の3つの柱による資質や能力をバランスよく育んでいくことを目標としています。教科・科目も大きく改編され、「古典探究」や「日本史探究」など、「探究」の名の付く科目が7つ新設されます。新学習指導要領のキーワードは「探究」といっても過言ではありません。
英語の教科においては、情報や考えを的確に理解したり適切に表現したり伝え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力を育成することを目標に掲げています。そして、「読む・聞く・書く・話す」の4技能教育から「読む・聞く・書く・話す(やり取り)・話す(発表)」の5領域教育へと変わります。授業は原則としてオールイングリッシュで行われます。
英語の教科には「探究」の名の付く科目はありませんが、新設される「英語コミュニケーションI・II・III」や「論理・表現I・II・III」の科目においては、他の科目と同様に主体的・対話的で深い学び(アクティブラーニング)の視点からの学習、いわゆる「探究型学習」が重要視されます。探究型学習では、「情報の収集」や「整理・分析」はもとより、生徒一人ひとりの課題を発見したり、解決したりする手段として「ICTの活用」が欠かせません。
第6回ESIBLA教育フォーラムでは、2022年度からの英語授業がどのように変わるのか、授業事例やICT活用例などを交えて詳しくわかりやすく解説します。
開催日時
2022年1月29日(土)
開 場:12時30分開 始:13時00分終 了:17時45分
開催形態
Zoomミーティングを通してのオンライン開催。
※後日、期間限定で見逃し配信いたします。
料 金
500円(税込)
プログラム
基調講演のほか、5つのウェビナーを開催予定です。
※ウェビナーの順番等は変更する可能性があります。
13:00~14:00 基調講演14:15~15:15 セッション1 A会場、B会場15:30~16:30 セッション2 A会場、B会場
※60分×2枠を同時配信予定。
16:45~17:45 総括講演
今求められる、探究学習のメソッドとしてのPBL
田中 茂範 先生(慶應義塾大学名誉教授、PEN言語教育サービス代表)
講演内容
現在の教育課題を挙げると、教科の分断化、教科教育と社会的現実との結びつきの弱さ、学習活動や演習の目的の不透明さ、評価システムの問題、受験志向への偏重の5つに要約することができるだろう。これに対して、新指導要領では、教科間の連携のための教科横断型の学び、教科教育に社会的現実を与えるための探究学習、有意味な演習の展開のための主体的・対話的で深い学び、新しい評価法としてのcan-doによる行動目標の設定、そしてよりよい生を生き抜くため、自分の人生を切り拓くことができるような生きる力の育成に重点が置かれている。この講演で注目したいのは、「探究学習」である。課題解決型の探究学習はいろいろな学校で実践されているが、その確固たる方法論があるとは言い難いのが現状である。そこでこの講演では、探究学習の方法論としてのPBLについて議論を深めたい。
田中 茂範(たなか しげのり)コロンビア大学大学院で教育学博士号を取得。コロンビア大学は教育哲学者ジョン・デューイ研究のメッカであることから、デユーイの著作にふれ、そこではじめて探究学習、プロジェクト学習について学ぶ。5年間茨城大学教養部にて教鞭をとり、1990年、慶應大学SFCの開設と同時に移籍。以降28年間にわたり、SFCを舞台に、プロジェクト学習(project-based learning)の実践を英語教育及びゼミにおいて行う。現在は、PEN言語教育サービスの代表として、高等学校などで探究学習プログラムのプロデュースや教材開発を行っている。業績としては100冊以上の著作、数多くの論文がある。
セッション1 A会場 14:15~15:15
~プロジェクト学習を通して育てる英語力と人間力~
登壇者
豊嶋 正貴 先生(文教大学付属中学校・高等学校教諭)
講演内容
新学習指導要領では、育成すべき資質・能力を「学びに向かう力・人間性等」、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」の三つの柱とし、その達成のために「主体的・対話的で深い学び(=アクティブラーニング)」を授業改善の視点として提案している。この内容を、自身の英語授業に反映させるためには、具体的な授業イメージや最終活動時の生徒のイメージを共有することが不可欠であると考える。本校、高校3年生の英語表現の授業では、高校3年間の英語の集大成として、発表活動(プレゼンテーション)に取り組ませている。単にあるトピックについて説明するのではなく、これまでに培ってきた知識と技能を総動員して、自身の主張を伝え、聞き手の考え方と行動を変えることが目標である。ここでは、発表活動を成功に導くための指導過程をできるだけ丁寧かつ、わかりやすく紹介していきたい。
豊嶋 正貴(としま まさたか)埼玉県出身。文教大学付属中学校・高等学校 教諭(進路指導部長・英語科主任)、文教大学国際学部講師、國學院大學教育開発推進機構講師。関西大学大学院外国語教育研究科博士課程前期課程修了。英語授業研究学会理事、ELEC同友会英語教育学会常任理事。文部科学省検定中学校教科書『NEW HORIZON English Course 1・2・3』(東京書籍)編集委員、文部科学省検定高等学校教科書『NEW FAVORITE Logic and Expression I』(東京書籍)編集協力、『コミュニケーションのための総合英語』(共著、朝日出版社)ほか。平成30 (2018) 年度「第12回キャリア教育優良教育委員会、学校及びPTA団体等文部科学大臣表彰」受賞
セッション1 B会場 14:15~15:15
中学校英語における「探究型学習」の実践の現在〜青翔開智中学校・高等学校での「探究スキルラーニング」を中心に〜
三浦 永理 先生(青翔開智中学校・高等学校)
講演内容
鳥取県にある青翔開智中学校・高等学校では、2014年の開校当初から、探究基礎を中心に様々な教科が探究を中心に構成されています。その中でも特徴的な取り組みのひとつが「探究スキルラーニング」です。本校では、これからの社会における課題発見・課題解決に必要とされる資質やスキルを「探究スキル」として設定しており、それらを育成するのが「探究スキルラーニング」で、探究的な学びを全ての教科で実施しています。学校図書館を情報ハブとして「探究スキルラーニング」を行うことで各教科の授業と探究基礎の授業をつなぎ、教育課程全体を通して探究活動の質を向上させることを目指しています。中学校は、高校に先んじて学習指導要領が改定されました。本校では、中学校の英語から、英語を使いながら、ライティング活動、発表の活動、動画制作やポスター制作まで、様々な取り組みを「探究スキルラーニング」として学びをデザインしています。今回は、中学校での授業の実践を中心に、英語科においてはどのように探究的な学習に取り組んでいるか、またどのようにICTを活用しながら授業を行なっているかをお話しします。
メッセージ
英語の授業を鳥取で「探究」する毎日も2年目。今回の場は、中学校英語の事例を通して、授業のあり方を一緒に「探究」できる機会にしたいと思います。
プロフィール
三浦 永理(みうら えり)青翔開智中学校・高等学校英語科教員。主に中学生の英語の授業を担当。東京都出身。早稲田大学国際教養学部卒業。大学では舞台芸術、哲学や宗教、イスラーム地域研究と幅広い分野を学ぶ。在学中は、イスラーム地域への関心からトルコへ留学。大手芸能プロダクションでマネージャーをつとめるも、教育者を志し一念発起。教員免許を取得する傍ら、タクトピア株式会社でインターンを経験し、鳥取県の青翔開智へ。
セッション2 A会場 15:30~16:30
クリティカルに思考してアクティブに活動する
〜英語4技能5領域の指導と観点別評価
登壇者
講演内容
布村 奈緒子 先生(ドルトン東京学園)
来年度より高等学校で新学習指導要領が全面実施されます。「英語4技能5領域」や新科目「論理表現」をいかに指導するのか、そして「観点別評価」をどのようにして行うのか、悩まれている先生方も多いのではないでしょうか。中学校の英語初級者から高等学校の生徒まで、それぞれの英語のレベルに応じた生徒がクリティカルに思考しながら、アクティブに活動する授業実践例を「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に学習に取り組む態度」の3観点の評価と関連付けてお話したいと思います。一部ICTの活用事例を含みます。中学校「英語」高等学校「英語コミュニケーション」「論理表現」の授業で行うことができる実践例です。
布村 奈緒子(ぬのむら なおこ)ドルトン東京学園中等部・高等部教頭兼英語科主任。東京都立国際高等学校、東京都立両国高等学校・附属中学校を経て、2020年より現職。英語を話すだけではなく、課題解決力とコミュニケーションを伸ばす授業実践事例多数。高等学校学習指導要領(平成 30 年告示)解説外国語編・英語編執筆協力者。著書に『テキスト不要の英語勉強法「使える英語」を身につけた人がやっていること』 (KADOKAWA)。現在、NHK ラジオ英会話『英語教師が考える「英語学習のエッセンス」』コラム連載中。
セッション2 B会場 15:30~16:30
花園式グローバル人材育成法
~スーパーグローバルZENコースの軌跡~
登壇者
中村 広記 先生(花園中学高等学校)
講演内容
本校は、明治5年に臨済宗大本山妙心寺の宗門子弟の教育機関として創立され、来年、創立150年目を迎える、長い歴史のある学校である。建学の精神は「禅のこころ」であり、創立以来、禅の精神を根本に据えた教育を展開してきた。今、日本は「少子高齢化」という極めて大きな問題に直面し、これまでの教育だけでは、将来持続可能な社会を構築していくために不可欠な人材を育成することが出来なくなっている。「10年後、20年後の世界で活躍できる人材を本気で育成したい」という信念から、本校では2016年、これまであった中高一貫コースを廃止し、「スーパーグローバルZEN(禅)コース」と「ディスカバリーコース」という2つの全く新しい6年一貫コースをスタートさせた。スーパーグローバルZENコースは「禅ZENの心を有する真のグローバル人材を育成する」という教育目標を掲げている。6年間に及ぶ、妙心寺の全面バックアップによる本格的な修行体験を通して、心身と共に自身のアイデンティティを磨き上げ、卒業後は「海外大学」に正規留学する。我々はこういう教育こそが「世界に互するグローバル人材」を育成すると確信している。このセッションでは、6年目を迎えた本校のスーパーグローバルZENコースにおいて実施してきた様々な教育活動をできる限り詳細に紹介し、参加者の皆様が携わっておられる教育の現場において取り入れることのできるような教育プログラムをご提案したいと考えている。
プロフィール
中村 広記(なかむら ひろき)1968年京都生まれ。大学卒業以来、花園中学高等学校に勤務し、今年で30年目を迎える。難関国公立大学合格を目指す特進Aコースの担任や統括責任者を長年務めた後、進路指導部長、一貫教育部長を務め、現在は副校長の職に就き、グローバル教育推進室統括責任者を兼任。2016年にスタートした「スーパーグローバルZENコース」「ディスカバリーコース」の開設責任者である。
総括講演 16:45~17:45
「英語」×「ICT]×「探究」ー未来の教室(STEAM)から教科横断型ー
誰一人取り残さないー生徒の気づきと学びの最大化ー BYOD6年の実践
登壇者
講演内容
米田 謙三 先生(関西学院千里国際中等部・高等部)
関西学院千里国際中等部・高等部(SIS)は、関西のグローバル教育のリーダーを目指して大阪インターナショナルスクール(OIS)と共に1991年に設立されました。このSISとOISは、関西在住の帰国生・一般の日本人と外国人のために、日本や海外の最高の教育システムや教育技術を、共有・採択して実践するために設立されました。 SISとOISの生徒達が共有する「SOIS」キャンパスでは、彼らが多くの時間を一緒に過ごし、双方が刺激しあう国際的な学習環境が作られています。探究・課題解決、コミュニケーション、自立・自律そして貢献、多様性の尊重の4つの力を身に付けるため、21世紀を見据えた実験校として様々な取組を行っています。探究型の学び、アクティブ・ラーニング(A・L)型の学びでは、総合探究科を中心に7年生(中1)から12年生(高3)まで課題研究に取り組んでいます。(「知の探究」という探究の思考法や情報収集の方法を教える新しい授業を開発し、探究の手法を学び、リサーチやフィールドワークの実践を行うという段階的なカリキュラム)個を支援する組織的な取組も充実させている。特に、ICT化は進んでおり、他校に先だって、6年前からBYODを活用した授業の実施、成績処理システムのオンライン化などの取組を進め、教員の自由度と業務の効率性も向上させてきた。またSTEM科も立ち上げ、未来の教室のモデル校ともなり、子ども達のワクワクを起点に「知る」と「創る」の循環的な学びを実現することも目指しています。
メッセージ
「STEAM教育と教科横断授業の事例」「ICT活用とすぐに使える英語で使えるアプリ・ソフト紹介」
プロフィール
米田 謙三(よねだ けんぞう)
関西学院千里国際中高等部 教諭 社会科・情報科・総合探究科(英語免許所持)進路センター長主任・高2学年主任、文部科学省:教科情報高校学習指導要領担当・学習指導要領等の改善に係る検討に必要な専門的作業等協力者、総務省:青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース委員、経済産業省:未来の教室STEAMライブラリーWG委員、内閣府他6省庁共催:高校生ICTカンファレンス実行委員長、警察庁:児童のスマートフォン利用に関する効果的な広報啓発に関する研究会委員 など 教育委員会・教育センター・学校・塾などでセミナー・講演多数、探究、英語、STEAM、ICTなどの著書多数
・関西学院千里国際中高等部
コメント
チケット情報
このチケットは主催者が発行・販売します
第6回ESIBLA教育フォーラム
500円
お支払い方法
 PayPay(残高/ポイント)
PayPay(残高/ポイント)- Yahoo!ウォレット(クレジットカード)
-
Yahoo!ウォレットに登録されたカードのみ利用可能です。詳細はこちらをご確認ください。
チケットの取出し方法
お問い合わせ先
- メールアドレス
このイベントを見ている人にオススメ
読み込み中